 |
|
|
|
|
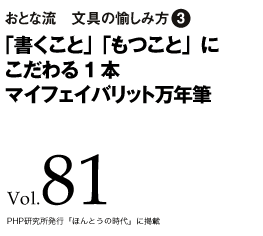
|
|
 |
|
本来「筆記」という行為は、言葉を選びとり、文章にして、
伝え、残すといったコミュニケーションの原点である。
パソコン全盛時代の今、文字を書かなくなったといわれるが
それでも、筆記具を代表する万年筆の人気は高くなっており、
「書く」道具としてだけでなく、「もつ楽しみ」を享受する人も増えている。
すっかりワープロ・パソコンのある生活に慣れてしまい、文章を「書く」機会が減った。これは世界的な傾向であろう。書かないと字がまます下手になるとか、漢字を忘れてしまうと言われるが、全くそのとおりで時々反省する。
今も原稿を書くのはパソコンでなく、手書きにこだわり続ける方も多いが、確かに手書きにはパソコン文字にはない味わい・魅力があることは否定できない。
普段の生活において全てを手書きに変えることは難しいが、「ここぞ!」と気持ちを伝えたいときには、やはり手書きで文を綴りたいもの。たとえば、「ラブレター」「お礼状」「どうしても伝えたいときの抗議文?」その伝達力は、さすがに文章力によるが、手書きだと意気込みは必ず伝わる。
さて、「書く」という行為には「書く道具」と「書かれるもの」が必要だが、そのなかでも、万年筆という存在は、重鎮的存在であり、最近では、文房具屋以外の業態でも取り扱われる場面も増えている。
もともと、「万年筆」とは18世紀中ごろイギリスで誕生した。それまでヨーロッパでの主要な筆記具とは羽ペン。昔、音楽室に貼ってあったポスター。音楽家たちが羽ペンをもっていた姿を思い出すが、ベートーベンやモーツアルトの時代にはまだ万年筆が普及していなかったのだ。彼らは蝋燭だけの暗い部屋で、すぐにすり減ってしまうペン先を何度も削りつつ、構想を楽譜に書き溜めたという。インク壷が楽譜にこぼれてしまうアクシデントもあったようだ。
その後、本体にインクを溜めることができる画期的な金属製ペンは、まさに「泉のようなペン」として誕生。英語で万年筆をFOUNTAIN PENというが、単にインクが泉のように出てくるという意味だけでなく、豊かなイマジネーションまで湧き出るという意味も含まれているのではないかと思ったりする。
さて、この万年筆は日本には19世紀末に上陸した。毛筆文化が浸透していた日本社会にいきなり横書き文化の道具である万年筆が登場し、最初は使う側にも戸惑いがあっただろう。
その後、20世紀に入り国産の万年筆第1号が完成、そのときには、日本の文字に合う形に改良され、それのち国内使用も盛んになる。
あれから、約100年。万年筆はワープロ・パソコンの利便性とは違う魅力で、人々を魅了し続け、とくに高級万年筆は人気が高い。
一説に万年筆は「男性の刀である」ともいうそうであるが、確かに「知性とセンスの象徴」であろう。さりげなく、内ポケットからこだわりの1本がさっと出てくると、その人の内面がわかるような気がする。
さて、そろそろ年賀状を用意する季節。今年は印刷して終わりではなく、手書きのメッセージを一筆入れてみるのはいかがなものか。 最後に「万年筆」の日本語訳が気になるが、「1万年後も使える筆記具」という意味が有力とのこと。
定年後のコミュニケーションライフにぜひ愛用されることを、おすすめしたい。