 |
|
|
|
|
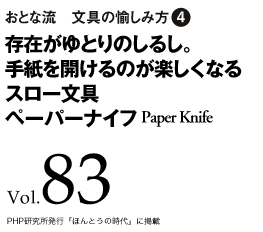
|
|
 |
|
郵便屋さんの手により届けられた手紙を、机の引き出しからさっと取り出して、開封する。
送り手の気持ちを大切に、そしてゆとりをもって受け止めるには、欠かせない。
デジタル時代が進んでも失くしたくない、書斎の小道具でもある。
出張から戻り、上着を脱いで机にたまった郵便物を、秘書の報告を受けながら開封する。その手元にちらりと光るペーパーナイフ…。
とある外国映画に出てきそうな1シーンを想像してみたが、なぜかペーパーナイフは「粋で出来る紳士」の象徴というイメージがある。子供時代には馴染みがなく、ペーパーナイフで開封することは「大人のたしなみ」であると気づいたのは、最近である。
個人的な話で恐縮であるが、いつも時間に追われ、たまった郵便物をビリビリっと手で裂いて、あとでしまった・・・と後悔することがいかに多かったか。なぜ手で開けてしまったか。道具を取り出す時間がもったいない。早く中を見たい・・。
そんな性急な気持ちがせっかくの手紙たちに対し、悪いことをした。
とくに大切な方からの手紙は保存版であるので丁寧に取り扱わなければならない。という反省から、きれいに開封できる専用道具ペーパーナイフの存在に興味をもつようになった。
手紙を開けるなら、手持ちの鋏でもよいのでは。もちろんそうであるがよりスマートにきれいに開封するという点で、さらに見た目も楽しいとなるとやはりペーパーナイフである。(最近は、鋏とペーパーナイフがセットになったものも増えている)
そもそもペーパーナイフとはどこで生まれたのか。ナイフ自体が洋物であるから、和紙の文化の国の道具ではなさそうだ。
いくつかの文献を当たってみるとどうやら、明治時代の雑誌は折りっぱなし、つまり紙のふちが断ち落とされていない「アンカット」の状態であり、この本は、書店での立ち読みはもちろん、袋の部分をカットしない限り読めないものだったそうで、そのルーツは、といえばフランスの装丁本にいきつく。片手にペーパーナイフをもち、ページの袋をカットしながら読書をするというのがしゃれたフランス流書斎での過ごし方だった。
そこから生まれたペーパーナイフ。もともと本を読むための必需品であったものが、今やレターオープナーとして広く使われるようになったのである。その切れ味はもちろんのことであるが、最近はデザインや素材にこだわるものも増えている。もともとは西洋の書斎文化から入ってきたこの小道具、最近では日本の伝統的技術や工芸の魅力を生かした「ジャパニーズペーパーナイフ」も登場し、人気を集めている。有田焼のものは美しい色彩と繊細さ、温かい質感でギフトにも喜ばれる。また最近では、新潟生まれの「紙で作ったパーパーナイフ」なるものも登場して、スマ―トな切れ味、デザイン性と安全性に富む点で評判がよい。
手紙を書く、送る・・・そして一呼吸し、心を落ち着けきれいに開封、中身をじっくりと拝見する。
心を結ぶコミュニケーションが、ペーパーナイフをもつ楽しみからも広がりそうである。
書斎を彩る小道具としても、ぜひおすすめしたい。また最近はギフトとしても喜ばれる。贈ることで、気が利いていると思われるアイテムのひとつである。