 |
|
|
|
|
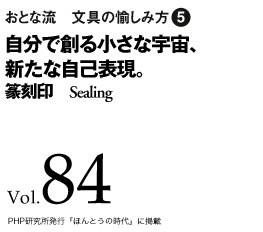
|
|
 |
|
「捺す」という行為は、責任や自覚を促されるもの。
日本の日常世界で、「はんこ」は社会人の必需品。
今、その「はんこ」もビジネスでの証明に使うものから、楽しいコミュニケーションの道具へと代わり、静かなブームになりつつある。
届いたハガキの文面最後に篆刻印をみつけたとき、「お、やるなあ」と、相手のセンスの良さに感心する。
封書も然り。単なる糊付けよりも、篆刻印で封緘してあると、姿勢を正して、ペーパーナイフで開封せねばというかしこまった気持ちになるものだ。
日本では、印鑑は社会人の必需品で、認印・銀行印・住所印・役職印から大切な実印まで、ゴムから漆に石材まで・・・と用途も素材も実に多様で豊富。時には自分の財産を守ってくれる、そして自分の「身分」を照明する絶対的存在として、人々の生活に浸透してきた。もちろん安価な認印の使われ方を見ると日本人独特の儀礼的な使い方である面も感じることもあるが・・・。しかし、最近ではこのような生活必需の儀礼印だけでなく、自分を表現する「ゆとり」の小道具として、篆刻印を作り、楽しむ人も増えている。わが銀座書斎倶楽部では、文化サロンと称し、毎月第3土曜に「篆刻教室」を開催しているが、最初はこつこつ約2年間続けるうちに当倶楽部の顔としてすっかり定着した。わずか2時間で、自分だけの本格的な「はんこ」が彫れるという取り組みやすさと、上海出身の新鋭若手書家 沈強先生の本場仕込の丁寧な教え方がうけている。ご夫婦で体験されたり、自分用の次は贈り物用にと何度も篆刻を楽しむ方や名前だけでなく好きな文字を彫ってみたいという方、また判子をもつ習慣のない西洋人にとって篆刻は大変神秘的で興味深いそうで体験に来る方もいる。
自分で石を選び、彫りたい文字を選び、それをデザインし、彫っていくという過程。わずか2~3センチ四方程度の世界と向かい合い、ただひたすらに彫っていくうちに、自分だけの世界に没頭する。そして遂に出来上がったものを捺してみる瞬間は何とも快感。
この出来立ての篆刻印をどこに捺そうか、誰に捺そうかとそわそわし、つい、これ自分で創ったんだと自慢したくなり・・・そしていつしか、そのこの篆刻印は、既製のものとは違う、大切な自分だけの「印」として、生活に馴染んでくるのである。
さて「篆刻」という言葉の意味をたどってみよう。もともとは、木や石、金などに「篆書」の文字で「印を彫る」ことと辞書にはある。この「篆書」とは、漢字書体のひとつで、秦の始皇帝時代以来、二千年以上も印章に使われてきた書体で、今も印の書体はこの篆書が主流という。
印や篆刻には面白い特徴がある。それは文字の周囲に枠があるということである。枠がその内に聖なる領域を作る。書にはその枠はない。だから印を捺すということは、聖なる空 間を印すということであり、神聖なる行為として中国では尊重されてきた。一種霊的な意味もあったそうだ。また篆刻印では他の実印などと比べると、文字が摩滅したり、ところどころに損傷があっても、それを自然の風化の美として尊ぶという。
確かにモノではあるが、文字を彫ることにより、何か生命的な存在に変化する。自分の分身と考えるのも、また面白いかもしれない。
そんなこんなで、篆刻印はちょっと神秘的で ある。
冬の休日。家でじっと籠っているよりも、マイハンコを彫りに教室通いなどしてみるのはいかが?