 |
|
|
|
|
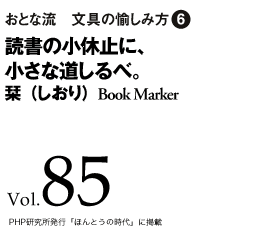
|
|
 |
|
読書を楽しむ人にとって、栞はなくてはならないもの。
ストレスフリーで本を開くことができ、その世界にすっと入っていける。
そんな機能以外にも、楽しい読書の演出ツールとしても活躍する。
気の利いたギフトにも最適な書斎の名脇役、「栞」(しおり)。
今や、ブックマークといえば、真っ先に思い浮かべるのはインターネット。みつけたお気に入りのページや頻繁に見るサイトのURLを登録し、いつでも呼び出せるようにする。そんな場面で「ブックマーク」という言葉をよく使うが、もともとは、字のごとく本に印を付け、見たいページをいつでも見られるようにするモノを指す。 日本ではそれを「栞」(しおり)というが、この栞という言葉には深い意味があるようだ。広辞苑によると、もともと「栞」とは山道などで木の枝を折りかけ、帰りの道しるべとすること、「枝折る」(しおる)という意味の雅語動詞からきているようだ。なるほど、道しるべというのは面白い。
確かに栞は、読書の道しるべである。味わいのある言葉だ。
また、「しおり」という言葉は、小学生のころ、「遠足のしおり」「修学旅行のしおり」で聞き慣れた感がある。
この場合の「しおり」は入門書とか、「手引き」という意味であるから、栞の本来の意味とも確かに通じている。
もし、栞がなかったら、読書はとたんに不便になる。目的のページを毎度探さねばならずいらいらしたり、またあるページを折ってしまい、本を傷めてしまうこともある。本を大切にする人にとっては不可欠な存在である。
では、人はいつからどんな栞を使うようになったのか。残念ながらいろんな文献を当たってもその記述が見当たらないが、言葉の意味から想像すると、古くは木片や竹片を用いていたのではないかと思われる。そしてやがて紙製や皮製、金属製といった多種多様な素材のブックマーカーが登場してきたようだ。
デザインも紙製であれば、名画や景色を印刷した安価なもの。また、欧米に行くと金属製や皮製の上質かつ装飾性高いものがいろいろ。先端に動植物や読書をイメージする装飾が施されたもの、観光地へ行けばその名所のシンボルの入ったもの。見ているだけでもわくわく。かさばることもないので、まさに「スービニエール」としても買い求めたくなる。現実的な機能としては本の栞であるが、旅の記念、旅心の道しるべとしての役割も果たしてくれる。
ちなみにこれまで見つけたブックマーカーでもっとも感激したのは、ニューヨークでみつけたチェーン型で上下の先端に動物や飛行機の装飾がついていたもの。
実は今も探しているが、なかなか見つからないのが、これまたニクイ。日本では見た目よりも機能性を重視したもの、使い方が目につく。ある会社の手帳にはレンズ加工したプラスチックのしおりがついている。また単行本では、栞紐のついたものが多い。文庫本の場合は最近少なくなったが、時々栞紐がついている本に出会うとうれしい。
最初にこれを考えた人は偉い!と思う。日々、本屋で本を買えば、広告の入った栞をはさんでくれるということが多いが、ここにはコマーシャリズムがちらり。これらの細やかな工夫やサービスは日本特有のものかもしれないが、これからは本の種類や読書の目的によって、栞も使い分け、時にはマイブックマーカーを使ってみるのもよいかもしれない。とある50代の男性が、当倶楽部の店内で、ヨーロッパから買い付けてきた金属製のブックマーカーをご覧になり、「これ、いいなあ」とつぶやき、立ち止まった。お連れの女性が「じゃ、プレゼントしてあげる」とお買い上げ。その紳士は恥ずかしそうに、でも顔をくちゃくちゃにして喜んでおられた。
本の好きな方であれば、そんな所にもこだわりたい。それが読書をより楽しくする。でも、きっと男性たちはそれを自分で買うのはちょっと恥ずかしい。
バレンタインや春のギフトの季節である。読書の好きな紳士たちに今年は「おしゃれな栞」を贈ってみてはどうか?「人生の道しるべにどうぞ」とメッセージを入れてみるのは大げさか?